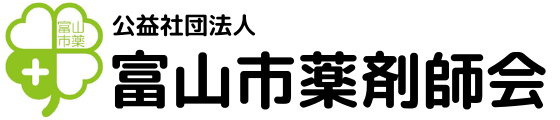【報告】R7.2.27(木)富山市薬剤師会学術講演会(サプリメントの基礎知識)
五福薬局実習生 熊谷綾乃
令和7年2月27日(木)に富山県薬剤師会館研修室とWEBとのハイブリットにて富山市薬剤師会学術講演会が開催されましたので報告いたします。
初めに、厚生連高岡病院 泌尿器科 医長 菊島卓也先生より「排尿障害の現場から―薬剤師が知るべき下部尿路症状の実践知識」という演題で排尿障害の概要と薬物療法のポイントについてお話いただきました。先生が勤めておられる厚生連高岡病院泌尿器科がその手術実績から、尿路結石治療や前立腺肥大治療に注力していることを冒頭で述べられ、後半で排尿障害の分類及び前立腺肥大症・過活動膀胱・神経因性膀胱の薬物療法のポイントと副作用管理について解説していただきました。排尿障害は長年継続して処方される患者さんが多く、経過で心疾患や脳血管障害を発症している患者も多いこと、そのうえ他院でデータ不明なことが多いことから、特に副作用の管理が重要であると説いておられました。私はまだ実習2週目で現場の経験も無に等しいです。それでも、先生が言っておられたように長期内服時の副作用の確認、及び気がついた点があれば医師に報告する、ということが薬剤師に実際に求められている任務であるということを実感することができ、身が引き締まる思いをしました。

続いて、一般社団法人ドーピング0会 代表理事 吉田哲郎先生より「薬剤師が知っておきたいサプリメントの基礎知識:頻尿向けサプリメントの実例を交えて」という演題で、どの業種も担ってこなかったサプリメントの専門家としての役割を薬剤師が担うために必要な知識についてお話いただきました。「サプリメントの専門家はどの業種が担うのか?」という問いに対する答えは未だ明確になされません。なぜならば、医師も栄養士も薬剤師も己の領分でないと考えているためです。しかし今日、サプリメントは普及してきており、患者さんにとって大変身近なものとなっています。そのなかで、薬剤師こそがサプリメントの安全性に関して積極的に介入できると先生はお考えで、その根拠及びどう介入すべきかについてお話いただきました。サプリメントは医薬品ではなく食品であることは周知の事実です。しかし、そこから一歩踏み込んで注意すべきことがあります。それは、薬と違って厳密な規制がされていないことに加えて知識がなくてもお金があれば作ることができるため、消費者が知識を身に着ける必要があるということです。このことについて私は今まで意識していませんでした。先生は「サプリメントは玉石混交、もはやほぼ石である」と言っておられました。よって、サプリメントを賢く選ぶための判断基準として、最低でも保健機能食品であることが必須であるとのことです。保健機能食品は一般食品とは異なりその機能性の表示を行うことができます。その中でも機能性表示食品は特定保健用食品に比べて申請が容易く、そのうえ自由に商品訴求を行えるために流行しているということを学びました。今回の講演では特に、サプリメントと医薬品の相互作用を調べるためにデーターベースを活用する方法を教えて頂きました。手順としては以下の通りです。
- サプリメントを成分に分解し、機能性成分を抽出する
- 成分のカテゴリーは何か、作用メカニズムを調査する
- その成分の相互作用について複数の調査ツールを用いて調べる
前述したようにサプリメントは患者さんにとって大変身近なものであるため、薬剤師がサプリメントの知識をもち、相談に乗ることがある種の信頼構築につながると先生は説いておられ、私も頷きながら拝聴しておりました。サプリメントと医薬品の相互作用を調べることは追加業務のように感じられますが、元の責務である医薬品同士の相互作用を調べることと同様のことを行えば良いと私は考えました。もっと言えば、医薬品を選ぶのは主に医師ですが、サプリメントは患者さんの意志で選ぶものなので、その機能性成分について時間の許す限り患者教育の一環として患者さんと一緒に調べるというのもありなのではないかと思いました。
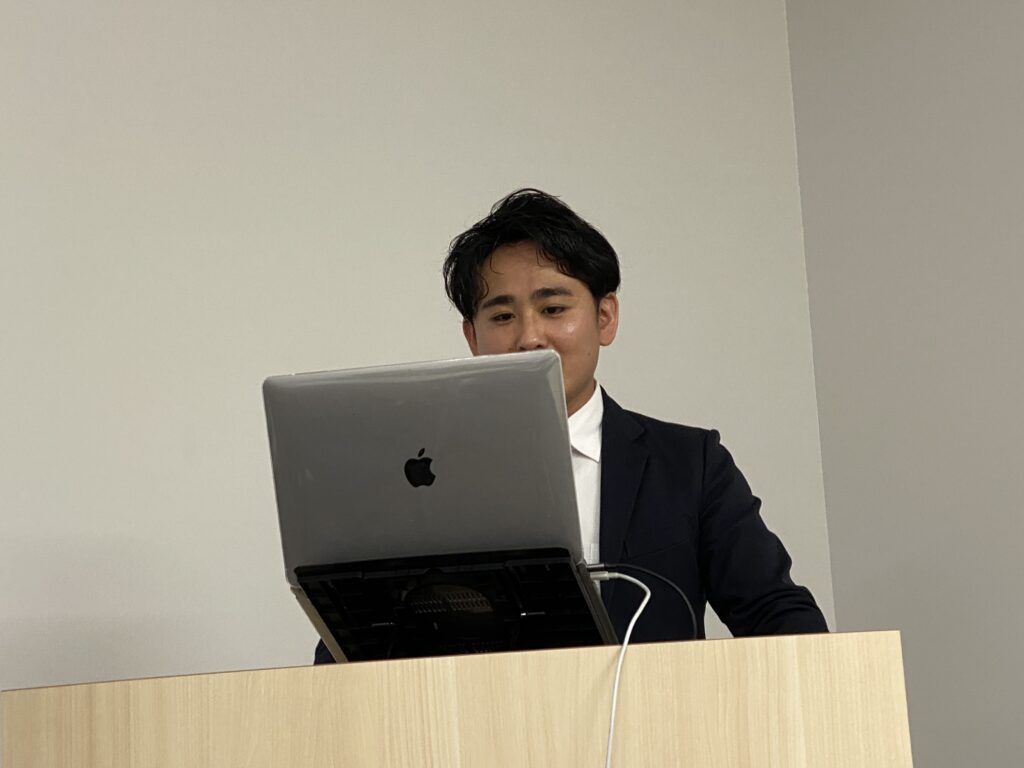
今回の講演は私にとって新たな知見が得られた、非常に収穫のあるものでした。貴重なご講演をしてくださった両先生に感謝申し上げます。